|
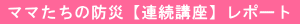
第8回 初期消火とケガの手当て
〜消防署で三角巾の使い方と初期消火を学ぶ〜 2012/11/19
「初期消火とケガの手当て」では中野消防署で三角巾を使って乳幼児のケガの手当てを学びました。初期消火の大切さを知り、実際に消火器での初期消火訓練体験をしました。
「火事だー!」と声をあげ、火元に見立てたコーンに消火器を噴射するママたちのたくましい姿。
―― 連続講座「ママたちの防災」の第8回は、区民活動センターを飛び出して消防署へ。イケメンの消防士さんたちから三角巾での手当ての方法と消火器の使い方を教わりました。
三角巾の意外なたたみ方に驚いたり、家庭用消火器は10数秒しか噴射できない(!)という事実に衝撃を受けたり。最後はご厚意で消防車での記念撮影までさせていただき大満足!
学んだことをほんの一部ですがご紹介します。
消火器での初期消火訓練
水の入った消火器で初期消火の訓練をしました。
- 消火の時はとにかく「火事だー」と声を出して周りに知らせる。
- 消火器を使うのは「火が小さいときのみ」、必ず「自分の逃げ道を確保してから」 ――家庭用消火器は10数秒噴射する容量しかない。コンロの火は消せても、例えばカーテンに燃え移ったら無理なので逃げる。
- 消火器の使い方 1.近づく 2.ノズル(ホース)を持つ 3.ピンを抜く 4.握って発射!
- 炎でなく火元を狙う。

三角巾を使ったケガの手当て
■包帯法
三角巾を細長く折った状態で傷に当て、止血のためきつめに巻いて結びます。片方の手を固定した状態で、反対の手をぐっと引っ張るのがしっかり巻くこコツ。反対側も同様にします。
耳が隠れると人は不安になるので、なるべく耳は出るように。

■腕の吊り方
 三角巾の端を肩にかけ、上と下の端を首のうしろで結びます。吊る位置は都度本人に確認しながら。高めの位置が楽な方が多いそうです。 三角巾の端を肩にかけ、上と下の端を首のうしろで結びます。吊る位置は都度本人に確認しながら。高めの位置が楽な方が多いそうです。
手の色(青くなっていないか)が見えるよう、指先が布からでるようにするのがポイント。

―今回のレポートは野田悠子さんです―
|


